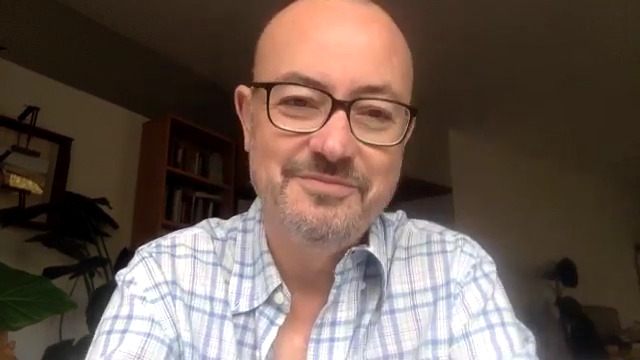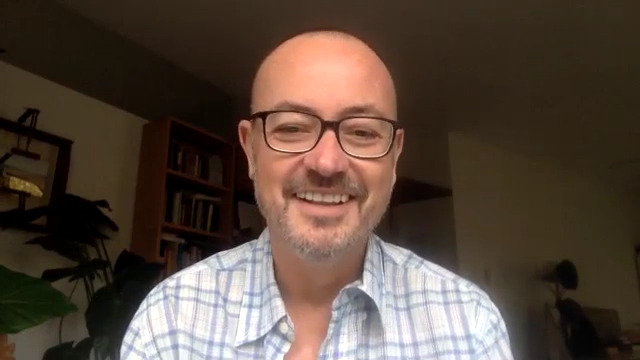東京国際映画祭公式インタビュー 2021年11月2日
『ザ・ドーター』
マヌエル・マルティン・クエンカ(監督/脚本/プロデューサー)
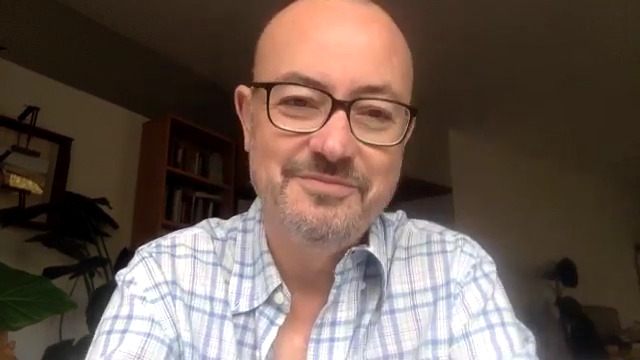
©2021 TIFF
『カニバル』(13年)が2014年に日本公開されて、その名が知られることとなったスペインの鬼才マヌエル・マルティン・クエンカ監督。彼の最新作『ザ・ドーター』は、『カニバル』にも似た葛藤を抱えた主人公の物語だ。収容所に入れられている少女イレーネは、指導員のハビエルに連れられて山岳地帯の一軒家に匿われる。妊娠しているイレーネの出産を手伝う代わりに、ハビエル夫妻は生まれてきた子を養子にするという条件をつけて…。大自然の中、密室劇のような心理戦にフォーカスしたサスペンス・スリラーだ。
――私が観たコンペの作品の中で、最もエンターテインメントしていました。
マヌエル・マルティン・クエンカ監督(以下、クエンカ監督):驚きです。エンターテインメント性が高いと言われるとは(笑)。なぜなら、私はスペインではそのように一切捉えられていないから。スペインでの自分は、人があまり見たくないようなものを見せつける映画人として捉えられているんですよ。
私としては、エンターテインメント性とかそういうことは一切考えないで、社会の矛盾や問題を見せていくということがすごく大事なので、ミステリーとかサスペンスのような要素を、恋愛ものの映画であっても必ず入れてしまいます。今回は、最後に大きな爆発のようなものを持ってこようとしました。
――日本でも公開された『カニバル』もそうでしたが、そういった問題の切り取り方が独特ですね。
クエンカ監督:今回の作品は、非常に原始的なものを描きました。それはふたりの女性が赤ちゃんを巡って争うということ。現代で起こりうることだけれども、同時に、2万年前に起こったとしてもおかしくないようなものだと思うんです。
――『ザ・ドーター』と『カニバル』に共通するのは、比較的長いショットが多いことですよね。
クエンカ監督:作品を撮るときは、カメラワークやポジショニングは全部自分でコントロールします。そしていつも、カットをなるべく少なくするのですが、カメラのポジションは、「何かが起こっているのを見ている傍観者」と捉えています。スリラー映画にありがちな手持ちカメラや、たくさんのカット割りは人工的だし、起こっていることをモデレーションしていく感じになりますよね。長く回せば回すほど、自然といろいろなものが聞こえてきたり、観客にとって興味や好奇心が掻き立てられるはずなんです。
――この作品のストーリーのインスピレーションはどこから?
クエンカ監督:ある作品がきっかけです。その作品そのものはそれほど心動かされなかったんですが、本作につながる一粒の種を見出しました。それは、なかなか子供に恵まれないカップルが、他の人の子供を自分の子供にしようとする、というプロットです。そこにヒントを得て脚本を書き始めました。
実は、私もパートナーと何年も子供が欲しいと言ってきたのですが、子供に恵まれなかったんです。だから、私自身も子供が欲しくても授からないという痛みが分かります。そしてその痛みは、人に一線を越えさせてしまう可能性がある。そこに興味がありました。
――まさか、ハビエルとアデラの気持ちが分かってこれを書いていたとは、全く想像つきませんでした。失礼いたしました。
クエンカ監督:いえいえ。私は彼らのように一線を越えているわけではないですが、感情が分かると、彼らの行動要因も分かります。『カニバル』もそうですが、“悪”はサイコパスから生まれてくるのではなくて、彼らのようなどうしようもない状況に追い込まれた人間が起こすことではないかと思うんです。人間というのは、人間的な共感や愛情など、最大の善も可能であり、それらをぶっ壊してしまう最大の悪も可能なものですよね。本作では、人は偉大なこともできるけれど、同時に、モンスターにも成り得るという矛盾を描き出したのですよ。
――『カニバル』の主人公も『ザ・ドーター』の主人公も両方とも、一見は善人に見えるけれども、実はすごく冷酷だということを持ち合わせてますものね。
クエンカ監督:人は悪の名のもとに悪事を働くわけではなく、善意のもとに悪事を働く生き物です。いい例は戦争。戦争するにあたって、みんな自国や国民にとって、これはすごく良いことなのだとして行う。人が他者の意見に耳を傾けるとき、愛や共感が生まれるのですが、蛮行は独善的な考えに囚われて、人に耳を傾けないところで生まれるものです。それを考える矛盾は、非常に興味深いのではないかと思います。残念ながら、人は社会的にも個人的にも、蛮行に引っ張られる傾向があると思いますしね。
『カニバル』の主人公は、最初はずっと自分の考えに囚われているけど、ある日突然、他の人に耳を傾け始めます。今回の『ザ・ドーター』はその逆で、あの夫婦はずっと人に耳を傾けてきたけれど、それが突然、自分たちのことに耳を傾け始めているのです。
――あの衝撃のラストですが、特に音にこだわった演出の意図は?
クエンカ監督:私は、映画の中で殺人の様子を露骨に見せるなど、映像的トリックは好きではありません。むしろ、音によってどこにカメラを置くかなど、音に重点を置いている部分があります。音というのは、映像よりも大きなイメージをもたらすもの。そのもの自体を見せないことで、観ている人がより想像力を掻き立てられます。
想像力を使うと、逆に現実味を増し、強い破壊力を持っていくものですよね。だから、実態を見せないことや、何千という言葉よりも音だけという方が、いろいろなものを引き起こし、現実をもたらして、リアルな記憶や感情、イマジネーションに繋がると思い、あのシーンを作りました。
――ロケ地の山は美しかったですね。
クエンカ監督:出身地のアンダルシアで撮影しました。本作は、時間の経過も非常に大事なので、実際に秋、冬、春と撮影をして、イレーネの妊娠のプロセスをリアルに見せました。私にとって自然の風景はスペクタクルであり、同時にミステリアス。すごく素晴らしい部分もあれば、脅威になる部分もある。この映画の中ではあの大自然を、登場人物のひとりのように扱いました。
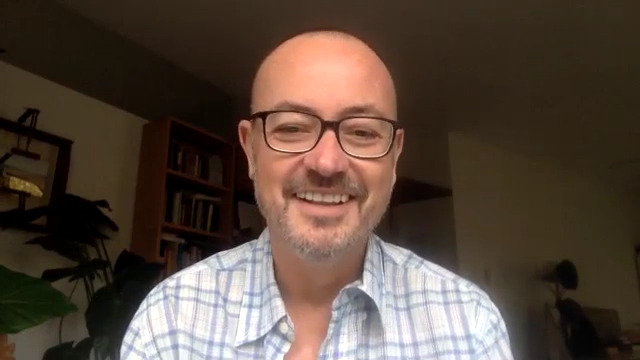
――自然といえば、ハビエルが天気を気にするシーンがありますよね。
クエンカ監督:そこは私がすごく好きなシークエンスです。オスマンが殺されて、イレーネが地下に閉じ込められているとき、アデラがイレーネのところに行って「母親は私よ」と言った後、ハビエルが外で煙草を吸っています。そこにアデラがやってきて、ほとんど何も会話がない。とんでもない状況なのに、ふたりは何も言葉を交わさないのですね。だけど、そこでハビエルが「ここ数日のうちにたぶん雪が降る」と言う。実は小津安二郎に対してのオマージュになっています。小津さんは必ず天気に関するレファレンスをしますよね(笑)。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)
第34回東京国際映画祭 コンペティション部門
『ザ・ドーター』

© 2021 Mod Producciones, S.L. / La Loma Blanca Producciones Cinematográficas, S.L. / La Hija Producciones la Película, A.I.E.
監督:マヌエル・マルティン・クエンカ
東京国際映画祭公式インタビュー 2021年11月2日
『ザ・ドーター』
マヌエル・マルティン・クエンカ(監督/脚本/プロデューサー)
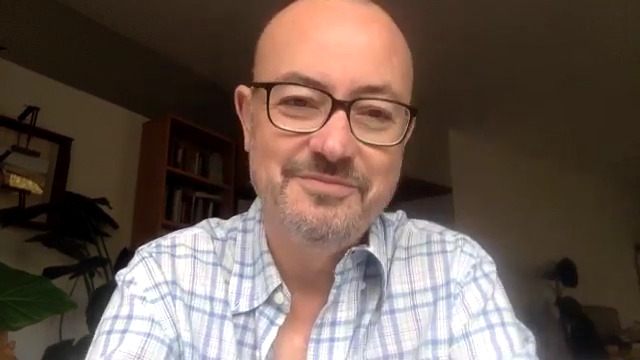
©2021 TIFF
『カニバル』(13年)が2014年に日本公開されて、その名が知られることとなったスペインの鬼才マヌエル・マルティン・クエンカ監督。彼の最新作『ザ・ドーター』は、『カニバル』にも似た葛藤を抱えた主人公の物語だ。収容所に入れられている少女イレーネは、指導員のハビエルに連れられて山岳地帯の一軒家に匿われる。妊娠しているイレーネの出産を手伝う代わりに、ハビエル夫妻は生まれてきた子を養子にするという条件をつけて…。大自然の中、密室劇のような心理戦にフォーカスしたサスペンス・スリラーだ。
――私が観たコンペの作品の中で、最もエンターテインメントしていました。
マヌエル・マルティン・クエンカ監督(以下、クエンカ監督):驚きです。エンターテインメント性が高いと言われるとは(笑)。なぜなら、私はスペインではそのように一切捉えられていないから。スペインでの自分は、人があまり見たくないようなものを見せつける映画人として捉えられているんですよ。
私としては、エンターテインメント性とかそういうことは一切考えないで、社会の矛盾や問題を見せていくということがすごく大事なので、ミステリーとかサスペンスのような要素を、恋愛ものの映画であっても必ず入れてしまいます。今回は、最後に大きな爆発のようなものを持ってこようとしました。
――日本でも公開された『カニバル』もそうでしたが、そういった問題の切り取り方が独特ですね。
クエンカ監督:今回の作品は、非常に原始的なものを描きました。それはふたりの女性が赤ちゃんを巡って争うということ。現代で起こりうることだけれども、同時に、2万年前に起こったとしてもおかしくないようなものだと思うんです。
――『ザ・ドーター』と『カニバル』に共通するのは、比較的長いショットが多いことですよね。
クエンカ監督:作品を撮るときは、カメラワークやポジショニングは全部自分でコントロールします。そしていつも、カットをなるべく少なくするのですが、カメラのポジションは、「何かが起こっているのを見ている傍観者」と捉えています。スリラー映画にありがちな手持ちカメラや、たくさんのカット割りは人工的だし、起こっていることをモデレーションしていく感じになりますよね。長く回せば回すほど、自然といろいろなものが聞こえてきたり、観客にとって興味や好奇心が掻き立てられるはずなんです。
――この作品のストーリーのインスピレーションはどこから?
クエンカ監督:ある作品がきっかけです。その作品そのものはそれほど心動かされなかったんですが、本作につながる一粒の種を見出しました。それは、なかなか子供に恵まれないカップルが、他の人の子供を自分の子供にしようとする、というプロットです。そこにヒントを得て脚本を書き始めました。
実は、私もパートナーと何年も子供が欲しいと言ってきたのですが、子供に恵まれなかったんです。だから、私自身も子供が欲しくても授からないという痛みが分かります。そしてその痛みは、人に一線を越えさせてしまう可能性がある。そこに興味がありました。
――まさか、ハビエルとアデラの気持ちが分かってこれを書いていたとは、全く想像つきませんでした。失礼いたしました。
クエンカ監督:いえいえ。私は彼らのように一線を越えているわけではないですが、感情が分かると、彼らの行動要因も分かります。『カニバル』もそうですが、“悪”はサイコパスから生まれてくるのではなくて、彼らのようなどうしようもない状況に追い込まれた人間が起こすことではないかと思うんです。人間というのは、人間的な共感や愛情など、最大の善も可能であり、それらをぶっ壊してしまう最大の悪も可能なものですよね。本作では、人は偉大なこともできるけれど、同時に、モンスターにも成り得るという矛盾を描き出したのですよ。
――『カニバル』の主人公も『ザ・ドーター』の主人公も両方とも、一見は善人に見えるけれども、実はすごく冷酷だということを持ち合わせてますものね。
クエンカ監督:人は悪の名のもとに悪事を働くわけではなく、善意のもとに悪事を働く生き物です。いい例は戦争。戦争するにあたって、みんな自国や国民にとって、これはすごく良いことなのだとして行う。人が他者の意見に耳を傾けるとき、愛や共感が生まれるのですが、蛮行は独善的な考えに囚われて、人に耳を傾けないところで生まれるものです。それを考える矛盾は、非常に興味深いのではないかと思います。残念ながら、人は社会的にも個人的にも、蛮行に引っ張られる傾向があると思いますしね。
『カニバル』の主人公は、最初はずっと自分の考えに囚われているけど、ある日突然、他の人に耳を傾け始めます。今回の『ザ・ドーター』はその逆で、あの夫婦はずっと人に耳を傾けてきたけれど、それが突然、自分たちのことに耳を傾け始めているのです。
――あの衝撃のラストですが、特に音にこだわった演出の意図は?
クエンカ監督:私は、映画の中で殺人の様子を露骨に見せるなど、映像的トリックは好きではありません。むしろ、音によってどこにカメラを置くかなど、音に重点を置いている部分があります。音というのは、映像よりも大きなイメージをもたらすもの。そのもの自体を見せないことで、観ている人がより想像力を掻き立てられます。
想像力を使うと、逆に現実味を増し、強い破壊力を持っていくものですよね。だから、実態を見せないことや、何千という言葉よりも音だけという方が、いろいろなものを引き起こし、現実をもたらして、リアルな記憶や感情、イマジネーションに繋がると思い、あのシーンを作りました。
――ロケ地の山は美しかったですね。
クエンカ監督:出身地のアンダルシアで撮影しました。本作は、時間の経過も非常に大事なので、実際に秋、冬、春と撮影をして、イレーネの妊娠のプロセスをリアルに見せました。私にとって自然の風景はスペクタクルであり、同時にミステリアス。すごく素晴らしい部分もあれば、脅威になる部分もある。この映画の中ではあの大自然を、登場人物のひとりのように扱いました。
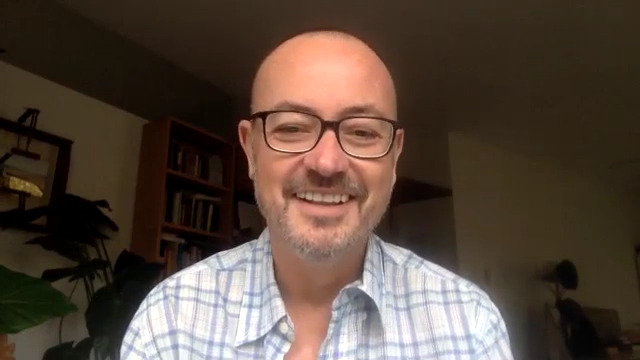
――自然といえば、ハビエルが天気を気にするシーンがありますよね。
クエンカ監督:そこは私がすごく好きなシークエンスです。オスマンが殺されて、イレーネが地下に閉じ込められているとき、アデラがイレーネのところに行って「母親は私よ」と言った後、ハビエルが外で煙草を吸っています。そこにアデラがやってきて、ほとんど何も会話がない。とんでもない状況なのに、ふたりは何も言葉を交わさないのですね。だけど、そこでハビエルが「ここ数日のうちにたぶん雪が降る」と言う。実は小津安二郎に対してのオマージュになっています。小津さんは必ず天気に関するレファレンスをしますよね(笑)。
インタビュー/構成:よしひろまさみち(日本映画ペンクラブ)
第34回東京国際映画祭 コンペティション部門
『ザ・ドーター』

© 2021 Mod Producciones, S.L. / La Loma Blanca Producciones Cinematográficas, S.L. / La Hija Producciones la Película, A.I.E.
監督:マヌエル・マルティン・クエンカ